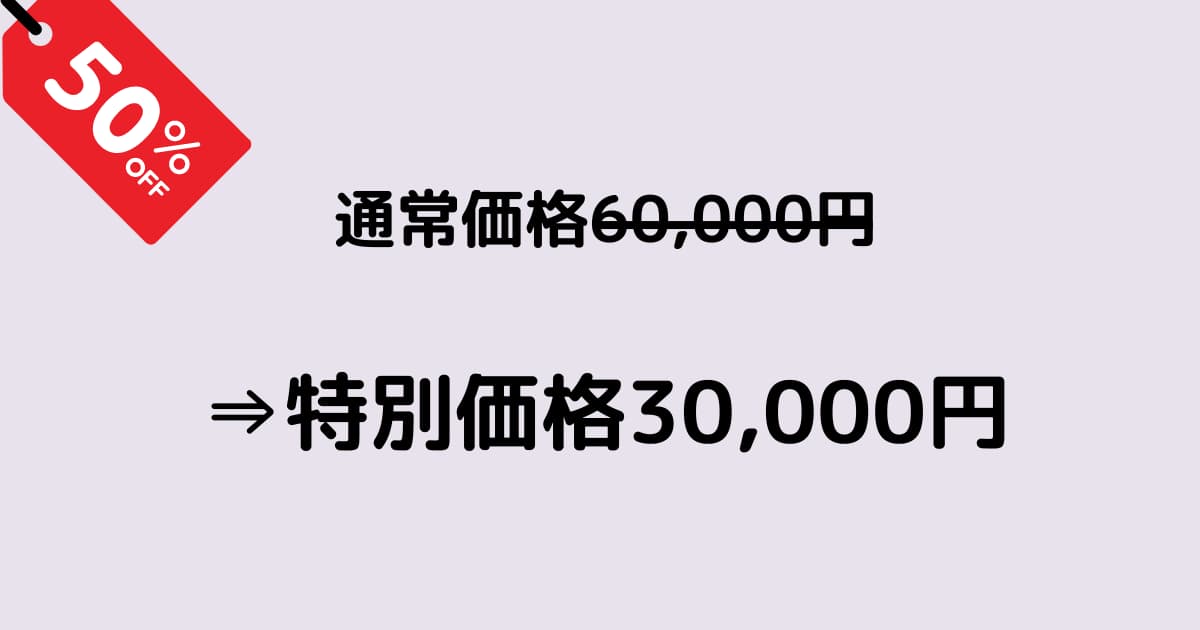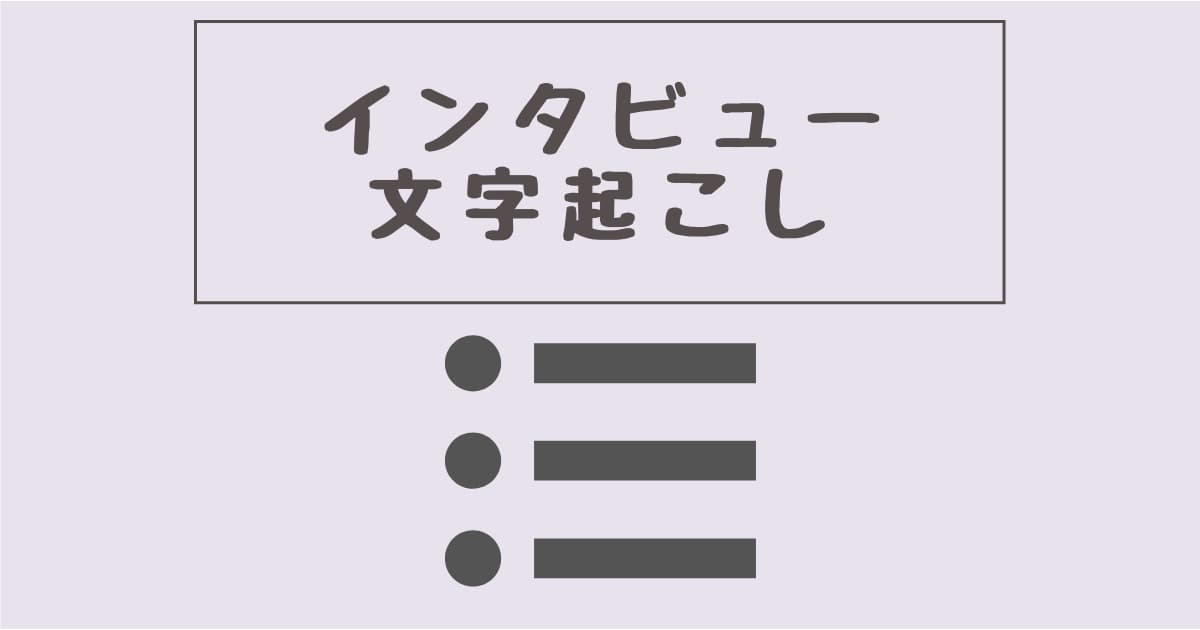
インタビューを記事化する前に、文字起こしを行うことが多くあります。
文字起こしは必ずしも必須ではないのですが、文字起こしをすることで、インタビュアーが記事化しやすい、内容を再確認ができるなどのメリットもあります。
文字起こしはリモートの普及の影響もありツールの性能も非常に向上しました。
ツールと手作業のリライトを行えば時間の3倍程度で文字起こしが可能になりました。
目次
インタビューの文字起こし
文字起こしとは
インタビュー記事を作成する場合の行程は以下の通りです。
- 企画書
- 質問シート作成
- インタビュー
- 文字起こし
- 記事化
詳しくは、インタビュー記事の書き方を大公開!を参考
文字起こしは、インタビューを終え記事化する前に、内容を文字化して記録する作業として行います。
文字起こしの段階には素起こしと、ケバ取り、整文があります。
素起こしとは、インタビューで話した内容を一字一句すべて文字化することを言います。
「あの~」「ええと」などの濁音や、単語の重複、言い間違いなども含めてすべて文字化します。
ケバ取りとは、濁音を削除して文字起こしする方法です。
整文とは、ケバ取りの上にさらに、話し言葉を書き言葉に直したり、ですます調に文章を整えたり、言い間違いなどを訂正します。
インタビューの文字起こしでは、インタビュアーやインタビュイーだけでなく、第3者が読んでも内容を理解することが重要です。
そのため、素起こしだとインタビュアーやインタビュイーだけでなく第3者も内容を理解することができないため、ケバ取りや整文が求められることが大半です。
メリットやデメリット
インタビューは最終的には記事化することが目的です。そのため、記事化の過程である文字起こしは必ずしも必要なものではありません。
文字起こしを行う場合は、依頼主が文字起こしを要求した場合と、インタビュアーが記事化するさいに、文字起こしした方が記事化しやすい場合に行われます。
文字起こしのメリット
1.動画再生の手間が省ける
文字起こしのメリット1つ目は、内容確認のために動画再生する手間が省ける点です。
後でインタビュー内容を確認するためには、音声を再生させる必要があります。
皆さんは動画を再生している最中は内容を理解できても、終了した途端、動画の内容を思い出せないということがありませんか?
大半の場合、動画を一度聞いて理解することはできないようです。
また部分的に内容を再確認したい場合、動画だとどこにどのような内容があるのかわかりにくいですが、文章化されていると必要な情報をピックアップして理解できるというようなこともあります。
2.内容の再確認ができる
文字起こしのメリット2つ目のメリットとしては内容の再確認が行える点です。
人間の脳は話している中で、自分が興味のあるところに注意が行きそれ以外はスルーしてしまうことがよくあります。
例えば同じ話を聞いても人により興味を持つ点が異なっていることはよくあります。理由は聞き手が興味のあることに注目しそれ以外のところはどうしても二の次になっているからです。
そのため文字化することで、内容を公平に再確認したり、インタビュイーの視点が本当に言いたかったことは何かを理解することが可能になります。
文字起こしのデメリット
文字起こしを行うデメリットは、想像以上に時間が掛かる点です。
録音した内容を完全に手作業で文字化しようとしたら、音声の再生とストップを繰り返しながら文字化する必要があり相当な労力がかかるのがイメージできるでしょうか?
文字起こしは、最近まではgoogleドキュメントが優秀でした。しかしリアルタイムや録音の再生ではうまく声を拾ってくれないためかなりの修正が必要でした。
しかし現在では音声の録音を一発でテキスト変換できるツールも出ていて作業がとても軽減されました。
ただ文字起こしの作業がかなり軽減されたといっても、一発変換されたテキストの修正や確認を行うと、目安としては録音時間の約3倍かかる計算になります。
文字起こしのやり方
文字起こしは、録音、ワンクリックでテキスト化、記事化の手順で行います。
録音する
インタビューでは、記事化するさいに内容確認ができるように必ず録音を取ります。
オンラインで行う場合は、録画と音声録音の両方を撮ります。訪問インタビューの場合は音声録音を撮ります。
録音で意識すること
静かな環境で録音する
インタビューをするさいは、静かな環境で行いましょう。会社であれば会議室で行います。
会社の会議室というのは完全な壁ではなく、移動可能なパーテーションであることが多いです。
そのためパーテーションで区切られた隣の声がうるさくて聞き取りずらいということもまま起こりえます。隣の会議室の稼働具合や、何に使うのかもチェックしておくと良いでしょう。
オンライン上で行うさいは、インタビューを行う部屋で家族の声が聞こえない時間や空間を選びましょう。また近所の工事などが騒音になることもありますので注意しましょう。
録音は、紙をバサバサめくったりドサッと置く音を予想以上に拾ってしまいます。そのため録音機器は、書類などの近くにはおかないこと、すこし手元から離したところに設置しましょう。
性能の良い録音機能を使用する
インタビューの録音では、パソコン、スマホ、レコーダーで録音する方法があります。
以前であれば、パソコンやスマホは多くの機能を所有しているため、録画や録音の機能にはコストが掛けられておらず機能レベルが低いと考えられていました。
そのため録音専用のICレコーダーが一番性能が良いと言われていました。
しかし最近はリモートが増えたために、各社パソコンメーカーやスマホ機種やアプリメーカーは、録画や録音機能の向上が行われました!
実際、私は最近パソコンを買い替えましたが、オンラインを行う際に必要なマイクの性能、録音機能、キーボードの打鍵音についてハッキリとした性能の向上が見られました。
以前はオンラインでパソコンに付属されたマイクでは聞き返されることもあり、外付けマイクが必要でした。しかし現在では、付属のマイクだけでも支障がなく聞き返されることもないので外付けマイクは使用する必要がなくなりました。
サウンドレコーダーの録音機能も以前よりクリアになりました。おそらくマイクの性能が上がったことで音声録音がクリアになったのだと思われます。
また以前はオンライン中にキーボードを使用すると、打鍵音が相手に響くという問題もありました。しかし今でも打鍵音はしますがソフトな打鍵音になりました。
そのため、リモートが急増する以前では、録音機能はICレコーダーの方が上だったかもしれませんが、今でははっきり言ってパソコンやスマホアプリのほうが録音機能が高いと感じました。
複数で録音する
インタビュアーが記事を書くさいは録音は命綱になります! 録音しとけばなんとかなるというのもあります。そのため複数で録音しておきましょう。
録音の性能は今ではICレコーダーよりパソコンやスマホアプリのほうが上であると紹介しましたが、複数で録音するという観点からであればICレコーダーの使用も候補に挙がります。
録音なんて一つで大丈夫、そう思うでしょう。しかし録音ミスというのは想像以上に起こりえます。
昔のカセットのようにガチャっという音とともに録音されるのであれば必ず録音されているのですが、今のは音がならないので押し忘れなども結構ありますので必ずスイッチが入っているのか指差し故障で確認しましょう。
また、パソコンやスマホは複数の機能が入っており、双方が干渉して作動しないということもあり得るからです。
新しいパソコン、新しい機能やアプリを使う場合は事前に動作するかを必ず確認しましょう。
ワンクリックでテキスト化
以前はかなりの作業量が発生した文字起こしも、現在では音声の録音をワンクリックでテキスト変換可能になりました。
ツールで音声をワンクリックで文字起こしした場合の正答率は約7割くらいが目安です。
ワンクリックで文字化したしたものを修正を加えて文字起こしを完成させます。以下その流れを解説します。
- ワンクリックでテキスト化する
- 再度音声を再生して追加文を挿入する
- ケバ取りを完成させる
- 整文する
まず、音声録音をツールでワンクリックでテキスト化します。
次に、再度音声を再生しながら、読み込まれなかった文章や、うまく変換されなかった文章を挿入していきます。
ポイントは、テキストの修正や必要ない部分の削除は行わず、音声を止ずに、とりあえず追加部分のみ挿入していきます。
音声を聞いたばかりなので内容を覚えていますし、読み込まれなかったり修正が必要な追記内容はすでにテキスト化して挿入してあります。
音声を止めて、テキストの削除や修正をして、ケバ取りや整文で文字起こしを完成させましょう。
必要があれば、やはり念には念を、もう一度音声を聞き流しながら文字起こしの最終確認を行います。
音声をワンクリックでテキスト化して、ケバ取りや整文の文字起こしの完成まで、音声時間の約3倍を見ておけば良いでしょう。1時間のインタビューであれば文字起こしに3時間かかるというふうになります。
記事化
ケバ取りや整文した文字起こしが終わったら記事化を行います。
1時間であれば約1万2千文字話していると言われており、文字起こしした文章の文字数も1万2千文字程度になっているでしょう。
1万2千文字程度の文章を、2,500~3,000文字程度にして記事を仕上げます。
人は会話の中で、同じことを別の言い方で説明したり、話を深めたり、展開させたりしています。また話が脱線したりということはよく起こりえます。
そのためそれらを1段落で表現できるところはまとめることで、、2,500~3,000文字程度の記事に仕上げます。
1時間のデータを3時間で文字起こし
文字起こしは、近年の急激な発達により、かなり時短が可能になりました。
もし文字起こしツールがなくて、人間の能力のみで行ったら、音声を再生とストップを繰り返して文字起こしをおこない、おそらく1時間当たりの8時間程度以上かかるのではないでしょうか?
googleドキュメントでは音声を読み込ませることでリアルタイムでも文字起こしが可能です。ただし読み込みエラーが多く初生するので、部分的なやり直しや修正が多く発生していました。そのため1時間当たり5時間程度掛かっていました。
現在では、録音からワンクリックで文字起こしが可能になり、再生~修正~確認までトータルで3時間程度あれば文字起こしが可能になりました。
まとめ
インタビューはオンラインであれば録画、訪問であれば音声の録音が記録として残っています。しかし録画や音声だと、保存するにはデータが重すぎたり、あとで再確認するのになかなか手間が掛かります。
そのため文字起こしして文章として残し、あとで誰が読んでも理解しやすいようにしておくと社内の評判も良いでしょう。
文字起こしをしておけば、インタビュアーやインタビュイーの視点からも、「あっこんなこと言ってたっけ?」というような新しい発見もあるはずです。
文字起こしをすることでさらなる発見やより深い記事を書くことが可能になります。
ツールが発達したといってもやはり文字起こしはかなりの手間が掛かりますが、メリットも多くあるのでぜひおすすめします。
また記事化にあたり文字起こしするには録音機器でクリアに撮ることも大切です。ぜひ参考にしてください。