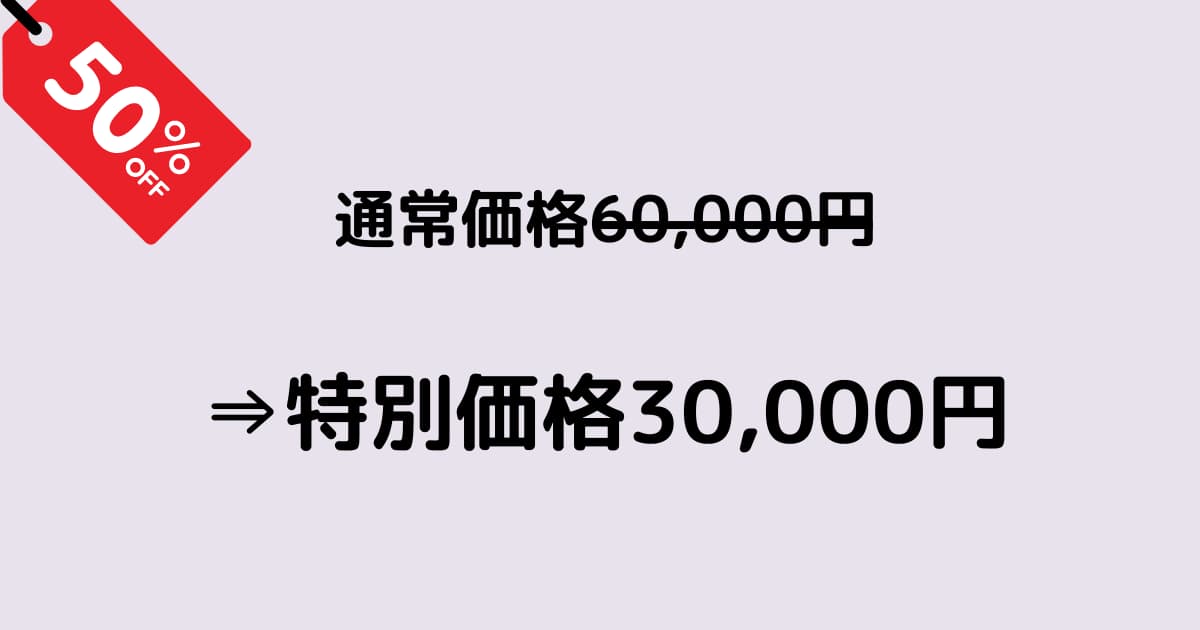企業のオウンドメディアの運営を続けていると、ネタ切れに遭遇している方も多いのではないでしょうか? そんなとき人気なのがインタビュー記事。
「どんな種類のインタビュー記事があるの?」
「インタビュー記事はどうやって作るの?」
「どのくらい時間が掛かるの?」
分からないことが多くなかなか実際にインタビュー記事作成まで行けないことが多いかもしれません。
そこで、インタビュー記事にはどのような種類があるのか? 書き方や掛かる時間などを解説しますので参考にして下さい。
目次
インタビュー記事の種類
インタビュー記事をネット上で見ることが時々あると思います。そんなインタビュー記事を掲載してみたいけど、どのような種類があるのでしょうか?
インタビュー記事の種類
インタビュー記事には以下のような記事の種類が合いrます。インタビュー記事を掲載することで、会社の内部の雰囲気を伝えることができます。
社長紹介
社長紹介はインタビュー記事の中でも最も需要が高いです。
既に自社サイトがあるのであれば、当然社長紹介ページは必須なので既に記事があるでしょう。
その社長紹介ページをインタビュー形式に書き換えても良いですし、別途別にインタビュー記事を追加しても良いでしょう。社長紹介をインタビュー記事にすると以下のメリットがあります。
- 他社との差別化
- Q&A方式を取ることで読者により伝わりやすい
社員紹介
社員紹介記事も人気です。
社員紹介記事を掲載することで、新卒募集のさいに社内の雰囲気を宣伝したり、企業向けに社内の雰囲気を伝えることも可能です。
ただ、社員紹介記事の場合は、必ずしもインタビューという形式を取らなくても作成可能です。
例えば、総務部などで質問を考えて、数十行程度で答えるという形式でも、充分にインタビュー記事の目的を果たすことができます。
書籍紹介
書籍紹介記事もおすすめです。
社員の中には、それぞれの分野の専門家がいることも多くあります。主に理系の技術者などをイメージしてもらえると良いと思います。その専門家は本を出しているなんてことはありませんか?
インタビュアーが本を出版した専門家に本についてインタビューします。
取引先などに、専門家としての社員の存在を知らせたり、企業のイメージ向上、商品のイメージ向上、社内の雰囲気を伝えることができます。
またこのような、Amazonなどをリンクした本の紹介を見たことがあると思います。これはもしもアフィリエイトを通じてAmazonアソシエイトを利用しています。本の表紙のイメージが読者にパッと伝わりやすいですよね。
お客様の声
商品を購入したお客様の声でもインタビュー記事がよく使われてます。
例えば、取引先に機械を売っていたとします。その機械の使い心地や、感想、使いやすさなどをインタビューします。
自社製品を褒めてもらった内容をオウンドメディアに載せるというのはなかなか難しいですよね。
しかしお客様の声、この場合は、ユーザーの声をインタビュー記事にすることで御社の製品を宣伝することが可能です。
担当者の声
本の紹介と被る点もあるのですが、担当者の声もお勧めです。
例えば機械であれば、機械開発の現場の声。開発に関して意識している点、苦戦した点、面白かった点、評判の良かった点などなどをインタビュー記事にすることで現場の声をオウンドメディアに反映することができます。
インタビュー記事を載せる媒体の種類
一般的にインタビュー記事と言うと、オウンドメディアに掲載するイメージがあるかもしれませんね。
しかし必ずしもオウンドメディアとは限らず、メルマガ、アプリなどに掲載するケースも多くあります。
インタビューのやり方
インタビュアーとインタビュイー
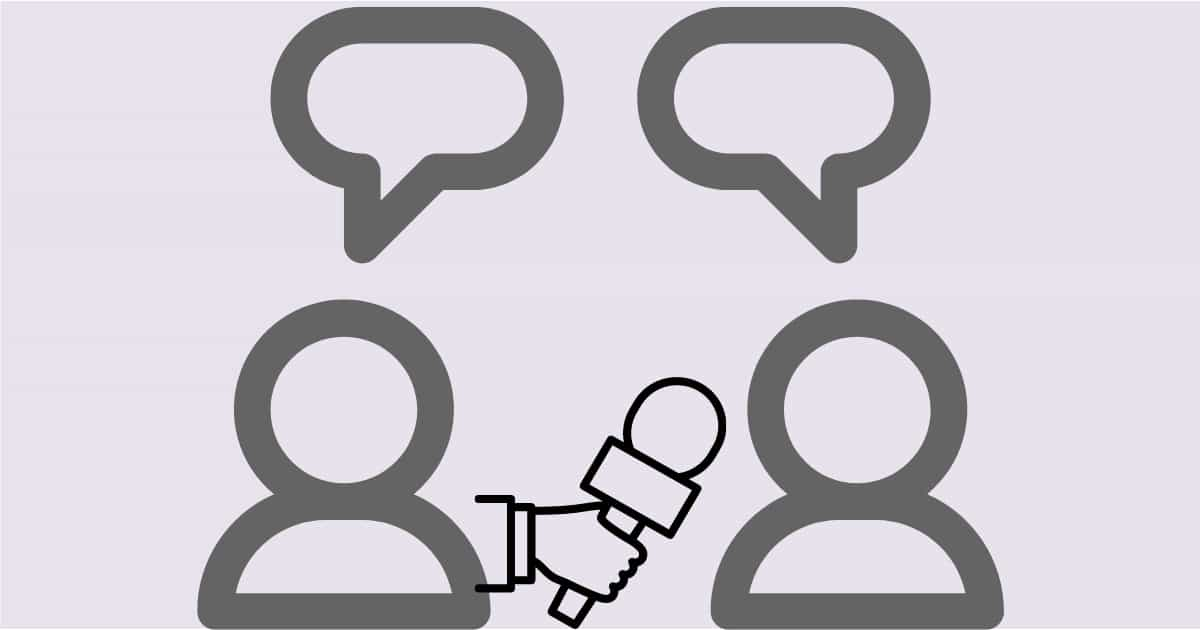
インタビューはQ&A形式で、通常2人、もしくは数人の対談形式になります。
インタビューはインタビュアーとインタビュイーで成り立ち、インタビューする側をインタビュアー、される側をインタビュイーと言います。
事前にインタビュアーが準備した企画書や質問シートに沿って行います。
企画書や質問シートは、事前にインタビュアーが準備し、インタビュイーに確認をします。インタビュイーは、質問シートに追加したいことや、インタビュー当日までに確認しておきたいことを調べたりします。
インタビュー時間は、案件によりますが約30分~1時間半程度になります。約30分~1時間程度であれば2,500~3,000文字程度の記事で完成します。
インタビュー記事の目的や、ターゲットはもちろん企業側で決めて頂きます。
ただ、企業によっては、インタビューを行うさいのインタビュイー探しからお願いしたいというケースもあります。
例えば、40代向けの化粧品のインタビュー記事を作成したいとします。その場合、40代女性で、その化粧品がスゴイ良かったと思うインタビュイーを探すことからも可能です。
インタビュイーは、基本的にネット上やSNS上で探すことが多いです。
インタビュイー候補探しや、インタビュイーへの依頼や日程調整など全部まとめてお引き受けしています。
インタビュー形式
インタビューのやり方は、オンラインインタビューとオフラインインタビューがあります。
オンラインインタビュー
リモートでの在宅仕事が増えてきたことに比例して、オンラインインタビューは需要がかなり増えてきました。
今まで生で行っていたオフラインインタビューも、可能な場合はオンラインに移行しました。
また、今までインタビュー記事はちょっとハードルが高かったけど、オンラインでインタビュー記事作成へのハードルがかなり下がりました。
そのためインタビュー記事を作成してみたいという需要がグッと増えました。
オフラインインタビュー(生取材)
今まで、一般的行われてきたオフラインインタビュー。
事前の企画書や質問シート作成までは、ネット上で行い、インタビュー当日はインタビュアーとインタビュイーが生で会って行います。
オンラインインタビューは、どうしても回線のタイムラグがあったり、空気間や、雑談という面ではやはり足りない面も。
しかしオフラインインタビューでは、話が深まったり、展開したり、緊張感やカジュアルな雰囲気生ならではですね。雑談に花咲くこともあるかもしれませんね。
インタビュー記事の書き方
それでは早速、インタビュー記事の書き方を具体的に公開します!
インタビュー記事の作成は、一般的なweb上の記事と違って、記事化へのさまざまな工程(準備~実際のインタビュー~記事化)を経る必要があります。そのため想像以上に時間が掛かっています。
もちろんインタビュアーが、インタビュー記事の書き方を習った先、その人の理解、経験などにより、書き方も大体の基本はありますが、当然個人差があります。
そのためインタビュー記事の書き方はこうだ!というのは一概には言えませんが、私が行っているインタビュー記事の書き方を隠さずバッチリ公開します。
1.企画書作成
まずは企画書を作成します。企画書とは、このインタビューは何のために行うのか?目的、誰をターゲットに行うのか? 内容が一目瞭然で分かるようにします。企画書の内容は以下の通りです。
- インタビュー記事の目的
- インタビューのターゲット
- インタビュー相手
- インタビューのテーマ・内容
例えばSEOライティングでは最初に記事構成を行い記事を書きます。インタビューでの企画書とはこの記事構成、いわゆる記事の方向性を示す地図のようなものだと考えて下さい。
以下に各項目について解説します。
インタビュー記事の目的
インタビュー記事の目的とはインタビュー記事を何のために書くのか?ゴールを指します。
本の紹介記事を書く場合、記事の目的は以下の通りです。記事の目的は必ずしも1つではなく付随して細かい目的もあるので一緒に記載し目的を明確化しましょう。
- 本の紹介
- サイトのEAT(専門性、権威性、信頼性)を高めるため
読者ターゲット
読者ターゲットとは以下の通りです。
- サラリーマンをやりながた大家(サラリーマン大家)を目指す人
ターゲットは複数挙げることができます。しかしある程度ターゲットを絞ることでピンポイントの記事を作成することができます。いわゆる刺さる記事になるのです。
インタビューテーマ・内容
テーマとは日本語に直すと主題と言うことになります。
- サラリーマン大家に興味がある人へ、「サラリーマン家主」入門の著者永井ゆかりさんに、サラリーマン大家が今旬な理由、本を書いた理由、内容などをインタビューする
企画書が一通り作成できたら、インタビュアーとインタビュイーの双方で確認してインタビューの方向性について再確認します。
2.質問シート
企画書をもとに、実際にインタビューを行うさいの質問シートを作成します。インタビュー当日ははこの事前に作成した質問シートの順に行われます。
質問シート作成はインタビュアーにとって一番力を入れるところです。インタビューはインタビュー当日が一番大きな仕事ではなく、事前準備の質問シートが一番力を入れる部分になります。
また質問シートを作成するさいに必要なことがあれば、ネットで調べたり、例えば本の紹介であれば本を読むこともあります。
インタビュー時間は1時間程度のインタビューの場合の質問数は~20個くらいになります。
質問シートが作成し終わったら、インタビュアーとインタビュイー双方で確認します。
質問シートが肝になりますので、企業側として質問シートに追加で入れたい項目や、伝えたい項目、エピソードなどをこの時に双方で確認します。
インタビュイーは、この質問シートの答えを事前に内容を決めておいていただけると当日のインタビューがスムーズにいくでしょう。
インタビュー
さて当日のインタビューです。
インタビューを直接生で行う場合は会社のオフィスなどで行います。
企画書や質問シートのやり取りはオンラインで行いますが、最後のインタビューのみ生のオフラインで行います。
現在ではインタビュー自体もオンラインインタビューの需要が高まっています。
インタビュー時間は約30分~1時間程度が目安です。質問シートの内容以外に、話しが展開したり、脱線したりすることもあります。その場合は1時間以上掛かることもあります。
また3人以上の対談形式で行う場合も1時間以上掛かることになります。
ちなみに1時間程度で人間が話す文字数は約18,000文字程度と言われています。最終的にはインタビュー記事にするのは2,500文字程度~3,000文字程度になります。
インタビュー当日は、少し緊張しますよね。しかし突然事前に準備していないことに質問が及んだり、予想外の方向性に行ってしまうということはないので安心して下さい。
インタビューは基本的には質問シートに沿って忠実に行われます。質問シートに無いことを質問することもありますが、それは質問シートの質問から更に内容を深めたり展開させたりする場合です。
インタビューは録画や録音を取ります。オフラインの場合録画をすることはなく録音のみを行います。
オフラインの場合は、インタビューが終わった後に撮影をすることもあります。
記事は公開する前に必ずこのような記事になったということをご連絡し確認していますので、思ったのと違う!という危険がありません。
文字起こしや整文
インタビュー記事は完成版だけでなく、実際のインタビュー記事の内容も確認できるようにしておきたいですよね。
記事作成をするさいには、インタビュー内容の文字起こしを行います。
文字起こしには素起こし、ケバ取り、整文と呼ばれる作業があります。
素起こしとはその名の通り素のまま起こすことです。ああぁ、うんうん、えっとなどの間投詞や、言い間違いなどもすべて正確に起こします。インタビュー内容の情報や雰囲気を正確に知るために良い方法ですが、インタビュー記事で素起こしは余り使われません。
ケバ取りとは、あぁ、うんうん、えっとなどの間投詞、言い間違いなどを取って文字起こしする方法です。
整文とは、ケバ取りした文章を話し言葉から書き言葉に整える方法です。
文字起こしを耳で聞いて文章化するのは非常に時間が掛かります。そのため一般的に文字起こしはツールを使って行われ、今は無料の文字起こしツールも多くあります。
例えば、googleドキュメントで文字起こしも優秀です。ドキュメント画面で、ツール⇒音声入力をクリックすることで音声入力をしながら文字起こしが可能です。googleドキュメントの音声入力で一度ザクッと文字起こしして、再度音声を聞きながら修正していきます。
文字起こしせず、録音のみでもインタビューの記録にはなりますが、音声のみだと、どこにどんな情報があるかですとか探すのが大変だったり、概要をサッと理解するには不便なため文字起こしを依頼されるケースが大半です。
記事作成
整文をもとに記事作成を行います。インタビュー時間が1時間程度の場合の文字数は、18,000文字。18,000文字を2,500文字~に記事化します。30分程度のインタビューであれば9,000文字を2,500文字~に記事化します。
そんなに削除するのか?と思うかもしれませんが、会話というのは、結構同じことを言い直していたり、脱線したりすることもよくあるからです。また重要な事を時間を掛けて説明した文を文章化するとかなり短くできることもよくあります。
記事化では、インタビュイーの言葉をそのまま使わないこともあります。
インタビュー記事で、最終的に何らかのCV(コンバージョン)を目的とする記事の場合は、CVの導線をしっかり引きます。
インタビュー記事を最終的に完成するまでには、聞き漏らしたことや、記事を書いていると更に疑問になってくることもあるので、その場合はインタビュイーにメールなどで確認をしています。
インタビュー記事が完成したら、このような記事で公開して良いかの最終確認を取りますので、予想と違う記事が公開された!ということはありません。
また記事の方向性も企画書や質問シートで事前に時間を掛けて作成し、インタビュアーとインタビュイー双方で確認して進めるので、予想外のインタビュー記事が出来てしまうということも充分避けることができます。
インタビュー記事のレイアウトデザイン
インタビュー記事では、質問と回答内容を順番に表示レイアウトします。
しかし、ネット上のインタビュー記事を読むとき、このような疑問を思ったことはないでしょうか?
「は? どこの文が質問文で、どこの文が回答文なの?」
「見出しの質問文を見ても記事の流れが分かんないよ!!」
そんなことがないように、質問シートの順番に、質問と回答内容、また見出しを選んでいきます。
カジュアルな雰囲気でも良いインタビュー記事では、レイアウトデザインとしてインタビューイラストアイコンを用いることもあります。
イラストアイコンでは、無料のイラストでも良いのですが、そのインタビュイーのオリジナルのイラストを準備するのも良いでしょう。インタビュイーの人柄や、雰囲気、トーク、間合いなどの空気間をイメージすることができます。
SEOは意識するの?
サイト運営やSEOについて多少なりとも学んだり経験のある方は、インタビュー記事ではSEOは意識するのか?疑問に思うことがあるかもしれませんね。
一概には言えないのですが、SEOを意識しないインタビュー記事のご依頼が大半です。やはり理由は、インタビュー記事は必ずしもオウンドメディアに掲載するわけではなく、メルマガやアプリなどに使用されることも多いからです。
またオウンドメディアに掲載する場合でも、社長紹介やお客様の声、担当者の声などはキーワードを意識して上位表示させる必要が無い記事が大半です。
またSEOで上位表示させようとすると構成に制限が出て難しいという面もよくあります。
そのため、SEO狙いというほどではなく、もし可能であればSEOも狙うという認識が良いと思います。そのため競合の記事に勝つために異常に長い記事を書く必要もなく、本当に必要な内容を、人が読むのに無理のない程度の文章量で記事を完成させます。
まとめ
以上がインタビュー記事の流れになります。
インタビュー記事の企画、質問シート、インタビュー、文字起こし、記事作成までのトータルで所要時間をハッキリ示すことは難しいのですが、大体30~40時間掛かると思います。
ただインタビューによっては、企画書や質問シートは依頼側で作成することもあります。
またインタビュー記事の記録としての文字起こしを必要としないケースなどもあります。
必要ない部分を省くことでもっと短時間でインタビュー記事を仕上げることも可能です。